社長の独り言
| <<前へ |
近況報告 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2024/01/16(火) 10:21
たまにはブログ更新させて頂いて、生存報告しておかないと…という趣旨で、あれこれと書かせて頂こうかと思います。
最初に個人的な話をさせて頂くのは如何なものかとは思いますが、ますは近況から。
実は2023年11月下旬に、実母が亡くなりました。
過去一年間ほど、内科的な病気ではないものの、外科的な理由で入退院を繰り返していたのですが、入院するたびに足腰の弱りが顕著になり、私も心配で実家へ行く機会が増えていました。
名古屋や関西方面での仕事を意図的に増やして、実家へ立ち寄る機会を半ば無理やり増やそうとしていたのも事実です。
夏に大腿骨骨折で手術を受けて入院。
10月20日頃に退院して、一か月足らずで心室細動により自宅で亡くなりました。
ちょうど亡くなった日の翌日には私が実家を訪問する予定でしたから、「あと1日、2日長生きしてくれれば…」と考えるのが人情。
しかしよく考えてみると、私が滞在中、夜間に心室細動でほとんど音も立てずに死なれたら…。
そのほうが嫌というか、トラウマになりますわ。
おおよそ84歳。
100点満点ではないかもしれませんが、長期間苦しむことなくピンピンコロリに近い状態で逝きましたので、上々の死に様かと思います。
割と広く知られていることではありますが、「入院すると、逆に寿命が縮む」のは、一定の条件下では真理かと改めて感じます。
比較的若い方が、治療のために入院するのは必要ですが、寿命が近い年寄りが、「治療のため…」と称して手術や入院をするのは考えもの…という意味です。
とまあ、こんなことがありましたので、11月下旬から約2か月にわたって、葬儀や法事や後片付けなどで忙殺されておりました。
合わせて、名古屋や関西方面で増やそうとしていた仕事の後片付けもしないといけませんでした。
今後の方針は未定なことも多いのですが、これで両親ともに鬼籍に入りましたので、今まで以上に土地に縛られず、自由に仕事をして生きていこうと思っています。
気楽に金儲けが出来ている訳ではありませんが、力尽きる最後の瞬間まで、前へ前へと前進するしかありません。
「泥水すすり草を?み~♪」となろうとも、前進あるのみです。
死ぬ前に、「あ~、しんどかった。やっと休める」と思える人生が、私の目標。
母の死が、私の褌(ふんどし)を締め直してくれたように思います。
さて、久しぶりなので、世間話も書かせて頂きましょうか。
最初に… ペットの話題で申し訳ありません。
2024年1月2日に発生した海保機と日航機の衝突事故を契機に、ペットを機内に持ち込むことの是非について、それなりに話題になっております。
私は是非の論争に参加するつもりはありませんが、一つ知っておいて頂きたいことがありましてね。
ペットを機内に持ち込むことに対して否定的な意見を見ていると、「アレルギー」あるいは「動物嫌い」を理由として挙げる意見が目立ちます。
私の狭い経験の中で語らせて頂いて申し訳ないのですが、知的障害者のかなりの割合で「動物(特に犬)の鳴き声を聞くと、パニック状態になる」人がいます。
個体の大小、声の大小に関わらず、とにかく姿を見たり、鳴き声を聴くとパニックを起こす人が少なくありません。
ネット上のどこを見ても、その手の話がありませんので、あえて書かせて頂きました。
もちろん個人差があるのですが、「悲鳴を上げて、シートベルト着用サインが出ていようがお構いなしで走り出す…」程度ならまだマシというレベルでパニックを起こします。
ペットの姿を見ただけで、そのくらいのパニックを起こす人間が少なからずいる…という現実を、飼い主さんは自覚したほうが良いですよ。
私は動物の中でも特に犬が大好きで、柴犬がお尻をフリフリしながら散歩している姿などを見ると、モフりたくてウズウズします。
でもね、世の中には色んな人がいて、自分にとっては家族同然でも、他人にとっては畜生だと思っています。
すでに一部の航空会社で、ペットの機内持ち込みを限定的に認める動きもあるようです。
商売ですから、自由にして頂ければ結構ですが、仮に私の同行者がペットを原因としてパニックを起こしたとしたら…。
「私は知らんよ」とまでは言いませんが、たとえ同行者でも、自らの身を危険を冒してまでは静止しないよ。
赤の他人なら、知らんふりを決め込むことは確実。
ペットの飼い主か、客室乗務員が何とかしなされ。
そんな安全運航へのリスクが潜んでいることを、賢明な皆様には知っておいて頂けたらと思います。
さて、最後に現在世の中を騒がしている話題で、「政治資金パーティー」関係のお話に触れておきましょうか。
これねえ、結構知っているような、知らないような。
おそらく、報道の影響で皆さんの事実誤認があまりに多く、一からそれらを説明していると、論文の一本でも書けそうなので、一つだけ指摘しておきましょう。
皆さんの周りにいる国会議員、その人は、国会議員になって御殿でも建てましたか?
それとも財産を食い潰しましたか?
それが真相ですよ。
御殿を建てた方がいらっしゃれば、大変興味があるので是非とも教えてください!
それでは、また!
2023年9月16日 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2023/09/16(土) 09:02
本日は2023年9月16日土曜日です。
9月も半ばとなり、残暑は厳しいながらも、朝夕には秋の訪れを感じることができるようになってきたように感じます。
今年の春は野球のWBCで、そして現在はラグビーワールドカップで勝手に盛り上がっております。
放映時間によっては寝不足になるから、キツイけど生放送で観たい。
例えテレビ中継の観戦であっても、スポーツを観戦したいという気持ちが湧いてくるということは、多少なりとも精神的な余裕があるのかな?…と前向きに受け止めております。
ドン底の気分だと、あらゆることへの関心が低下してスポーツを見ようという気にすらならない。
私はこのような傾向が出るので、「達者でやっている」とご理解ください。
すっかり忘れていましたが、今日から日本では三連休です。
秋の行楽シーズンで観光地が賑わう…とは思えないなあ。
物価高、厳しい残暑、そして何より皆さん自宅に引きこもることに慣れており、そして観光地へ行けば外国人観光客だらけ。
外出する気分になれない方が多いのではと予想しております。
さて、ビジネスの話の前に、2点ほど世の中の動きについての話題を。
まずは、ロシアによるウクライナ侵略の話題。
戦時ですから、「何が正しくて、何が?なのか分かりにくい」というのが、正直なところです。
傾向として明確なのは、
・ウクライナは、「都合の悪い情報は発表しない。しかし虚偽の発表はしない」
・ロシアは、「都合の悪い情報は発表しない。虚偽の発表も行う」
という事実。
戦況としては、「ロシアが築いた防衛線や地雷原の突破にウクライナ軍は難儀しているものの、着実に前線は前進しており、ロシアの損害は非常に大きく、戦線を持ちこたえることが難しくなっている。」
私の現状認識は、このような感じです。
そして近日中に、一部戦線でロシアの防衛網が崩壊し、ウクライナの領土奪還スピードが少し上がったところで、泥濘期→冬の到来で再び戦線膠着…となりそうな雰囲気。
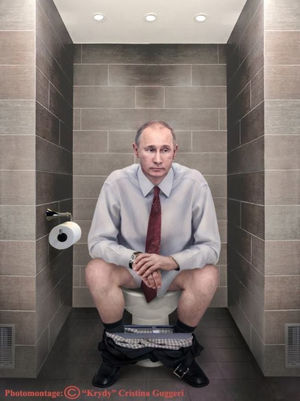
まあ、この人の権力と政治生命を守るためにウクライナの塹壕で死んでいくロシア兵は憐れなのですが、一方で「もっとロシア人を殺せ」という感情も無きにしも非ず。
私って野蛮ね。
あ、私は取るに足らない小さな貿易屋のオッサンですが、2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵略開始の一か月以上前から、ロシアによるウクライナ侵略開始を想定していました。
2022年1月のブログにも、
「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が懸念される中で、日本のマスコミは『コロナの陽性者が過去最高…』とか、日本人の民度は本当に低いね…」
と書かせて頂いております。
世の中には多くの頭脳明晰な方がいらっしゃいますが、「軍事力による問題解決はダメ!」という固定観念、前世紀のルールをプーチン大統領に適用して考えると、凡人以下の分析しかできない。
狂人は狂人を知る…ですよ。(笑)
もう一つ、世相のお話を。
2023年8月末から、福島第一原発事故のALPS処理水海洋放出が開始されました。
漁業関係者をはじめ、風評被害が予想される業界からは当然ながら反対意見が出たものの、国民の多数派は「放出するしかない」と科学的な観点から放出を受け入れているのかなと思います。
不動産バブルがはじけ、大量の失業者が発生しているが地方政府にも中央政府にもカネが無い…という危機に見舞われている中共政府が、失策を外敵に目を逸らすための手段として、海洋放出を徹底的に叩いていますな。

中共政府の皆さんもご苦労が多いでしょうが、頑張ってくださいね。
上の画像の人形は、ネットで購入しました。
いやね、中共政府の方々も大変だろうから、応援したくて。
これ、中国共産党の公式グッズかなあ?
??????
人形買って、応援してます!
…こんなことを書くと、文章の読めない方、文間が読めない方の双方からクレームが来そうですけど。
アホらしいですが、「文章の読めない方」と「文間の読めない方」の意味を、以下の回答例で解説しますね。
文章の読めない方へ
私は「応援してる!」って言ってるでしょ?
文間の読めない方へ
「日本語に込められた真意を察せよ」
「文間」まで読めるかどうかは、知性そのもの。
学歴や成績なんて関係ありません。
ご立派な学歴でも、日本語の文字は読めるが、文章を読めない、文間なんて考えない!…という方も少なくありませんのでね。
最後に仕事の話を少々。
中古自転車の輸出事業に関しては、大きな変化はありません。
東南アジア、アフリカともに需要は堅調で、海上運賃をはじめとする物流も安定しており、大過なく過ごせている感じです。
東南アジアが雨期の終わりに近づくこの時期、洪水等で一時的に需要が減少することもあるのですが、今年は問題なく雨期を乗り越えそう…と喜んでおります。
徐々に事業のウエイトを「自転車以外」の商材へと移行させていますが、約一年前の2022年8月から始めた新商材も、引き続き取り組んでおります。
結構良い結果が出ているのですが、他人の商売の良い結果なんて誰も聞きたくないかと思いますので、記事にしていません。
「良い結果を知りたい」なんていうのは、「パクりたい」と同義ですからねぇ。
以前から親しくさせて頂いている方には、洗いざらいお話しして商材確保にご協力頂いているのですが、まだ遠方の方にはお願いも出来ていません。
まだまだビジネスとして熟成が足りず、小さなトラブル発生と解決に振り回されているので、あまり大々的には出来ないんですよねえ…。
ちょうど輸出先国では政権交代がありまして、それに伴い様々な変化が起きています。
輸出先税関当局の責任者・担当者が変わると、「別の国」のようになることもあります。
直近ではお盆明けにコンテナを送ったのですが、新体制になって初めての現地通関では????、やはり多少の混乱があったようです。
もうしばらく、様子を見てからでないと怖くて話を広げられないな…というのが現状です。
たった一度の大きなミスで吹き飛んでしまうような小さな会社ですから、小回りを利かせつつも、慎重に事を進める必要があるのです。
本日はこのくらいにしておきましょうか。
またご報告させて頂きますね。
それでは、皆様お励みくださいませ!
今日までお盆休みです - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2023/08/15(火) 10:15
2023年のお盆休みは、台風7号の接近と重なり大きな混乱が生じました。
皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?
台風7号は関東地方に直撃するルートが予想されていましたが、予想よりやや西向きに進路を変えて紀伊半島へ上陸しました。
おかげさまで関東地方には大きな影響がなく、8月16日に予定されているコンテナバンニングも予定通り行えそうです。
お盆休みに入る前に、コンテナ輸送が難しいケースや、スタッフが出勤できないケースなどを想定した対応を準備していたのですが、幸いにも杞憂に終わりそうです。
良いことではあるのですが、「せっかく対策を練ったのに…」と少々残念な気持ちがあることも否定できない、性格の悪い私でございます。
私自身は8月13日に関西地方へ新幹線で向かい、仕事と実家訪問をさっさと済ませて、14日の夕方の新幹線で逃げるように東京駅へ戻って来ました。
滞在時間は約24時間。
とてもお盆の里帰りとは言えないものでしたが、15日は飛行機も新幹線も止まっていますので、こちらは目論見通りに事が運んだのでご機嫌です。
さて、前回のブログ更新からずいぶん時間が経ってしまいましたので、ご報告すべき仕事の話は多くあるのですが、一応今日まで当社はお盆休みとなっております。
なので仕事の話はお盆休みが終わってからということにして、今日は世間話でも書かせて頂きます。
ちょうど8月15日で終戦記念日ということもありますので、それに関連した話でも書かせて頂きますね。
2000年代初頭、私は国会議員の書生をしていたと紹介させて頂いたことがあります。
通常、ビジネスの世界では「政治と宗教の話はタブー」とされていますが、政治関係の仕事をしている人間が政治の話をタブーとするわけにはいきませんので、当然ながら毎日様々な方と政治の話をしておりました。
この時期になると、大東亜戦争(あえてこの表現です)における戦地経験者のお話も、多く聞くことが出来ました。
ほとんどは大正生まれの方々でしたので、2023年の現在では鬼籍に入られていることがほとんどで、もう直接お話を聞くことが出来ません。
すでに50歳を超えた、私のおじいさんの世代ですから…。
本当にいろんなお話を聞くことが出来ましたよ。
シベリア抑留経験者、インパール作戦の生き残り、戦艦大和の沖縄特攻生き残りの方etc... まさに歴史の生き証人である方々の話は、私の人生にも大きな影響を与えました。
細かい話は、また紹介させていただく機会もあるでしょう。
今日は、私が感じた「違和感」についてだけ書かせて頂きます。
戦地経験者の方のお話に対して、違和感を感じた訳ではありません。
私が感じた違和感とは、戦地経験者の方々と、戦争経験者の方の違いです。
分かりやすく言うと、戦地を経験した人間と、当時の子供とでは、全く話が?み合わないほど違う。
そんな感想を持った次第です。
一例をあげると、戦地経験者からは、あまりの物量の違いを体感して「こりゃあ勝てねえわ…と思った」というお話をよく聞きました。
小難しい話をするのではなく、「相手は腰だめで機関銃をぶっ放してくるのに、こっちは一発ずつバンバンと撃ち返すだけ。勝てるわけねえ…」といった話ですね。
一方で、当時子供だった世代の話としては、「喰うものが無かった。ひもじかった。」という話が代表的かな。
それに加えて、軍部や政治批判が多いのも特徴的かな。
違和感の正体は、戦地に行ったわけでもないガキ(当時)は能書きが多く、実際に戦地へ行った大人(当時)は、自分の経験のみを語る傾向にあったということです。
年齢的には一回りくらいしか違いがないのに、別の国の人と話をしているみたい。
そんな感想を持ったことを、「違和感」と表現させて頂きました。
2023年現在では戦時中にガキだった方々も、すでに80歳代半ばから90歳代に差し掛かろうとしていて、お話を聞ける機会も少なくなっています。
彼らの世代は、幼少期は戦争で大変な苦労をし、戦後の日本の発展を支えてきた方々なので、大いに敬意をもって接するべきであると思います。
ただ、彼らの戦争体験談は子供としての体験談ですから、子供向けの体験談としては大いに価値があるのですが、それ以上では無いということです。
分かるかなあ…?
なんだか大いに誤解されそうな気がしますが、人の話を鵜呑みにするのではなく、横からも斜めからも色んな目線で見て考えたほうが良い。
その一例として、戦争経験を語る人に「あなたは子供だったでしょ?」などとツッコミをしてみると、客観的に物事を見れるのではないか?
そんな話だとご理解ください。
中国への牛肉不正輸出事件の考察 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2023/05/31(水) 14:46
本日は2023年6月1日です。
2023年5月27日付のニュースで、
『「この店の肉は密輸」輸入禁止の中国で“ブランド和牛”…闇ルートを追跡取材』というタイトルのニュースが流れておりました。
当社は牛肉の輸出を行った経験は無いので、牛肉という商材に関しては全くの素人なのですが、「輸出業者」である点と、輸出先が「カンボジア」という2つの点では一定の知見がありますので、この話題に触れたいと思います。
最初にお断りしておきますが、当社は不正輸出などとは全く無縁であり、いくら叩いてもホコリの一つも出ない絶対的な自信があります。
だからこそネタとして取り上げておりますし、輸出業者全体の信用を保ちたいのと、主要取引先国の一つであるカンボジアの名誉のためにお話しさせて頂いているということをご理解いただければ幸いです。
最初に元ネタをご紹介させて頂きます。
引用元はテレ朝ニュースで、元記事はコチラです。
ポイントを抜粋しますと、
・日本からの牛肉が輸入禁止のはずの中国で、なぜ「和牛」が流通しているのか追跡取材した。
・日本からカンボジアへ向けてコンテナ船で輸出された冷凍牛肉が、香港を経由してカンボジアへ向かうはずが、和牛が入ったコンテナは密かに香港で荷下ろしされ、中国本土へ送られた…。
ということで、関税法違反と家畜伝染病予防法違反の疑いで、中国出身の容疑者3名が逮捕されたようです。
「中国出身」だけれども、日本風氏名の容疑者のようですから、掃いて捨てるほど日本に住んでいる「なんちゃって中国残留孤児関係者」かもしれません。
今は知りませんが、かつての中国では金さえ出せばいくらでも本物の戸籍が偽造出来ましたから、当時は貧しかった中国から、大挙して偽物の中国残留孤児親族が日本へ入国し、日本国籍を取得していました。
私はそういう方々を「なんちゃって中国残留孤児関係者」と呼んでいる次第です。
既にご存知の方もいらっしゃるでしょうが、実はカンボジアという国は、日本からの牛肉輸出量が第一位です。(2019年で約880トン)
カンボジアという、大変貧しい国に対しての輸出が第一位というのは意外に感じられるでしょうが、実際にはカンボジアで和牛なんてほとんど流通していません。
日本からカンボジアへ牛肉を輸出し、そのまま「カンボジア産の加工肉」として中国へ向けて輸出する…というのが鉄板ルートであることは、もはや公然の秘密と言っても良いくらいの話です。
中古自転車などの中古製品をカンボジアへ向けて細々と輸出している当社ですが、昼寝をしていても耳に入ってくるくらいの話でして、一般常識と言っても差し支えのないレベルの話です。
これ、日本サイドはカンボジアに対して牛肉を輸出しているだけなので、カンボジア側に商品を引き渡した後でどのような扱いをしていようが、日本側には何の責任も違法行為もありません。
事実上、日本産牛肉の輸入を禁止している中国に対して抜け道を使って輸出していることになりますが、日本の牛肉生産者は輸出が増えて喜びますし、輸出業者にも問題ないし、日本産牛肉を食べたい中国人も喜ぶ。
(クソ)中共政府による意味不明な日本産牛肉の輸入禁止措置に対して、民間人が知恵を絞って日本の法令に一切抵触することなく、売り手も買い手も皆が喜んでいる構図ですから、日本の国益的にも倫理的にも全く問題ない。
今回問題になって逮捕されたのは、カンボジアへ輸出すると申告しながら、「密かに香港でコンテナをおろすよう手配した」行為に対してです。
一旦カンボジアへ輸出してから中国へ輸出するよりも、「直接香港で下ろした方が儲かるじゃん」という理由で、犯罪となる行為に手を染めたから逮捕されたわけです。
カンボジアへ牛肉を輸出することが犯罪ではありませんので、くれぐれもお間違いのないように。
少々問題だと感じるのが、冒頭に紹介したニュース記事です。
例えば、和牛の生産者へのインタビューで、「不正に流出したやつでは、値段が安くなって、(和牛の生産が)厳しくなるのではないかと思います。」なんてことが書いてありますが、生産者への影響なんてある訳ない(笑)
お得意の誘導尋問みたいな手法で引き出したコメントなんだろうけど、犯罪的手法で流通コストを安く抑えただけの話で、牛肉生産者には何の関係もない。
「安く買い叩かれた和牛が…」なんて表現もありますが、日本の市場で安く買い叩いたわけでもない。
犯罪的手法で中国に入ってきた日本産牛肉を、中国人が中国人に対して買い叩こうが、日本には何の影響もないし、「お前ら勝手にやってろ」という世界です。
ご理解いただけるでしょうか?
さすがはテレ朝ですねえ。
こんな簡単な構図の話を、さも日本の牛肉生産者へ悪影響があるかのような話題に仕立て上げるとは。
私に言わせれば、こいつらの方がよっぽど犯罪的です。
復習を兼ねて、もう一度ポイントの整理を。
1.日本からカンボジアへ牛肉を輸出することは全く問題ない。
2.カンボジアへ輸出すると申告しながら、コンテナ船の経由地である香港でコンテナを下ろした中国系の人間が逮捕された。
3.日本の市場で牛肉を安く買い叩いたわけではない、(というか、安く売ってくれるはずがない)
4.この単純な話を、テレ朝が恣意的あるいは無知により、日本の生産者の不利益になるかのようなニュースを流した。
というのが私の考察であります。
ハッキリ言って、無知あるいは悪意のあるマスコミに迷惑してるんですよ。
4月に特殊詐欺グループがカンボジアで捕まったという事件がありました。
その際も「カンボジアは詐欺グループが活動しやすい国?」なんてことを書いていたマスコミがありましたが、あんなのは特殊詐欺グループがコロナ祭りの影響でゴーストタウンのようになった「シアヌークビル」という中国人向けカジノリゾートのリゾートホテルを安く借りていただけ。
私に言わせれば、全てが検閲されて国民を監視し、一切の政府批判を許さないために「明るい北朝鮮」と揶揄されるシンガポールよりも、カンボジアの方がよほど透明性が高く自由な国です。
まあ多くの日本人はカンボジアと言えば「ポルポト」、「大虐殺」、「地雷」くらいのイメージしか持っていないんでしょうねえ。
一体、いつの話だよ?
そんなことをいつまでも言ってると、「日本が悪いニダ」と言っている国と同レベルですよ?
最近ね、カンボジアへ輸出した商品の代金を受け取る際に、やたらと日本の金融機関が煩いんですよ。
こっちは輸出商品の種類によっては経済産業省に事前確認も取って、税関の輸出許可も得て、代金を踏み倒されないかビクビクしながら、代金を支払ってもらい、貿易黒字に貢献してるのよ。
証拠となる書類も写真も全部揃ってる。
にもかかわらず、四の五の言われるから「いい加減にしろよ!」という気分なのでございます。
余計な手間ばかり増やされるので、少々「プンプン!」なものですから、お気を悪くされた方がいらっしゃれば、ごめんなさい。
法令に違反する行為を行っている業者なら「ビクビク」とするでしょうし、迷惑している業者は「プンプン!」であるということで、ご理解いただければ幸いです。
2023年5月の日記 - たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。 -
投稿日時:2023/05/27(土) 09:59
今日は2023年5月の出来事の中から、ちょっと気になったことをいくつか書いてみます。
1.キャセイパシフィック航空キャビンクルーによる中国人差別(?)問題
中国成都発香港行きのキャセイパシフィック機で、「毛布(blanket)が欲しい」と言うべきところ、「カーペット(carpet)がほしい」と間違った乗客に対して、「Carpet is on the floor(カーペットは床の上)」などと嘲笑した…という出来事。
この記事を読んだとき、私は「プッ」と吹いてしまいました。
決して悪意のある笑いではありません。
もし私が機内でこのやりとりを聞いていたら、ボケとツッコミのジョークかと思って、コーヒーを吹いていたかもしれない。
そういうニュアンスでの笑いです。
実は近日中に東南アジアへの出張を予定しているのですが、今回はキャセイパシフィック航空を利用しての出張になります。
どうでもいいニュースなんですが、久しぶりに自分が利用する航空会社なんで、ちょっと気になった次第です。
キャセイパシフィック航空を利用するのは、本当に久しぶりです。
過去には結構利用していたのですが、中国共産党の悪行によって「香港は中国になってしまった」のと、コロナ祭りのため長らく利用する機会を失っていました。
とはいえ、日本から東南アジアへ直行便が無いルートで行く場合は、香港か台湾経由のフライトが体力的には楽です。
香港や台湾経由だと、座席に座っているのが疲れてきた頃に中継地へ到着し、一休みしてから最終目的地へ向かうことが出来るためです。
本当は台湾経由で行きたいのですが、接続が悪くて総所要時間がかなり長くなるので現実的ではない。
キャセイを利用すると、香港からはクソみたいな中国人が多く乗り込んでくるので良いイメージが無いのですが、接続が良いので久しぶりに利用してみることにしました。
ほとんど全ての航空会社で言えることですが、日本発のフライトは機材も比較的新しく、上品な乗客が多いので比較的快適なフライトになります。
一方で中継地から目的地までのフライトは、東南アジアクオリティの機材と乗客になるので、日本発のフライトと比べるとクオリティが低くなる傾向があります。
このため例えば韓国の航空会社を利用すると、韓国までの短時間の高クオリティのフライトと、韓国から東南アジアまで長時間の低クオリティのフライトで旅することになります。
東南アジアの航空会社を利用すると、東南アジアまでの長時間の高クオリティのフライトと、短時間の低クオリティのフライトで旅することになります。
航空会社選びも、難しいですね~。
2.ジャパン・レール・パスの値上げ
日本人にはあまり縁のない話ですが、JRグループが外国人観光者向けに発売している乗り放題パス「ジャパン・レール・パス」が10月から7日券で29650円から50000円、14日券で47250円から80000円に値上げされるようです。
この発表に対して外国人からは不評のようですが、元々JRにとってはジャパンレールパスは何のメリットもないことは有名な話かと思います。
「外国人からもっと多くのカネを巻き上げろ!」…とまでは申しませんが、外国人観光客を優遇する必要はないと個人的には考えております。
私は「観光公害」と言われるほど多くの観光客が訪れる京都が故郷なのですが、日本人・外国人を問わずスーツケースなどの大きな荷物を持って路線バスに乗り込んでくる観光客に対して「あなたたちは来ないで欲しいな…」と常々思っております。
京都の路線バスの多くは赤字経営なので、正規運賃を支払って行儀よくバスに乗ってくれる観光客ならありがたい存在でしょうが、大きな荷物を抱えて一日乗車券なんかで乗り込んでくる観光客は迷惑でしかない。
JRも同じで、正規運賃を支払って乗車してくれる観光客ならありがたいことでしょうが、ジャパンレールパス利用者なんて存在は、収益に貢献しないばかりか窓口対応などで人的リソースを割く必要がある迷惑客以外の何者でもない…と考えるのが自然かと思います。
「大金持ちの観光客だけ来てほしい」のが理想ではありますが、現実的ではありません。
そんなに大金を使わなくとも、宿泊先のホテルから駅まで、あるいは駅から観光名所まで1,000円ほどのタクシー代を使うだけでも地域経済に貢献できます。
バスや電車に乗るなら、正規運賃くらいは払いましょう。
飲食費をケチってコンビニやファストフードで済ませるのではなく、地元の飲食店を利用するのも良いでしょう。
入場無料の神社仏閣へ行くなら、奮発して多めにお賽銭を入れるのも良いでしょう。
とまあ、外国人観光客に対しては、JRの正規運賃くらい払ってよ…と思いますし、日本人観光客に対しては、能書き垂れるのはカネを落としてからにしてね…と思う次第です。
3.犯罪組織が活動しやすい?カンボジアに詐欺団拠点、日本人19人拘束…
これは4月のニュースなのですが、5月に入ってからも続報で特殊詐欺に関する容疑で再逮捕されたりと、少々日本を騒がせておりました。
私は4月にカンボジアへ渡航していたのですが、深夜に現地へ到着して翌朝のニュースがこれだったので、少々インパクトがありました。
結論から言えば、決して犯罪組織が活動しやすい国ではありません。
他の東南アジア諸国と比べても、ごく普通の国です。
マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金を監視する国際組織、金融活動作業部会(FATF)は2023年2月会合においてカンボジアをグレーリストから外していますし、マスゴミさんによる憶測の見出しでしかありません。
グループが滞在していたのはシアヌークビルという港町なのですが、少なくとも10年前までカンボジアの原風景を残した街でした。
しかし中国資本に街の多くが買い占められ、あっという間に違う街に変貌。
今は中国人向けのカジノリゾートみたいな感じです。
コロナ祭り開催中の2022年に行ってみたら、ゴーストタウンのようになっていましたので、安価で高級リゾートホテルの部屋を借りることが出来、日本への電話代も安いので狙われたのかな?…と思っております。
4.長野県中野市で4人が死亡した立てこもり事件
殺された被害者にとっては、たまったものじゃない事件です。
容疑者を擁護するつもりは毛頭ありませんし、ちょっと違った観点での感想を。
都市部で生まれ育った人間には理解しがたい一面が、農村部には垣間見れることがあります。
容疑者はいわゆる「地方の名家の長男」で、金銭的な面では比較的恵まれていたであろうと想像できます。
しかし別の見方をすると、地方の名家の長男ってやつは、百姓という職業に縛られ、土地に縛られて転居もままならず、地方独特の人間関係に縛られるという、がんじがらめの不自由さがあります。
万事に当てはまることですが、良い面も悪い面もあるということです。
この容疑者の父上は市議会議員だったようですが、政治家も職業(政治家)と土地(選挙区)と人間関係(有権者)に縛られた不自由極まりない職業です。
今の私自身はその正反対で、職業も土地も人間関係も、一切束縛されることを拒否した生き方をしていますが、もし束縛された状態で生きていたら非常に大きなストレスを感じ、ねじ曲がった感情を抱いていたのではないかと思います。
「職業も土地も人間関係も、全て捨てても良かったのに」
事件を起こした容疑者に対しては後の祭りですが、多くの方がこれらを「捨てることが出来ない」と思い込み、ねじ曲がった感情を自分の中で増幅しているのではないかと危惧する次第です。
殺人までには至らなくとも、他者や社会に対してねじ曲がった感情を持つ方が少なくないと感じています。
大丈夫だよ。日本では全てを捨てても、生きていけるから。
一度きりの短い人生、自由に生きな。
自分の中に妙なマグマをため込んで爆発しないようにね。
| «前へ |
 ログイン
ログイン